
昨年(2000年)は、私の仕事に一つの転機が訪れました。ミュージシャンと知り会っても、音楽の話、世間話をして、必要以上に踏み込まなかった私が、ある若手のグループと深く関わることになり、そのサクセス・ストーリーを間近に見守ることになったのです。その若手グループ〜Souliveとの最初の出会いは、ライターのM君に誘われていった、3月にアーヴィング・プラザというクラブでの、ジョン・スコフィールドの新作”バンプ”の発売記念ライブの時でした。オープニング・アクトで現れた彼らのパフォーマンスは、久しぶりに、血湧き、肉踊るというエキサイティングなもので、早速、彼らのファースト・アルバム”Turn
it out"を買い、しばらく、凄いバンドを見つけた、と吹聴しまわりました。これらが、Jam Band ムーヴメントとの本格的な、関わり始めとなったのです。
しばらくロードにでていたSouliveは、5月にNYに戻り、フランチャイズのウェットランズ・プリザーヴに出演。この時の模様は、ジャズ・ライフのNYリポート(2000年7月号)に寄稿すると同時に、私の吹聴をきいたヴィデオ・プロデューサーのS氏が、スカイパーフェクTVの深夜のNY音楽紹介番組に、取りあげたのです。そして、6月のバワリー・ボールルームでのライブは、ヴィデオ・カメラを廻していたN氏のプッシュで、9月のNHKBSのゴールデン・アワー番組に、ハイビジョンでオンエアされるという、僥倖に恵まれました。
結成から1年にして、東海岸のクラブ・サーキットでは、有名バンドとなっていた彼らに、メジャー・レーベル各社も触手を伸ばします。Souliveのゴット・ファザー的存在の、ジョン・スコフィールドの推薦によるヴァーヴと、メデスキ、マーチン&ウッドや、チャーリー・ハンター、ジャズ・マンドリン・プロジェクトらと契約し、Jam
Band 路線を押し進めていた、ブルーノートの一騎打ちとなり、ブルース・ランドヴァルの熱意が実って、このバワリー・ボールルームでのライヴの直前にブルーノートと、契約するはこびとなりました。 NYのインディ・レーベル、ヴェロアからでたファーストアルバムのアートワークも、60年代ブルーノートを意識していた彼らから見れば、Dream
comes trueといったところでしょうか。メジャー契約と、ツアーが一段落つく秋には、セカンド・アルバムのレコーディングが決まったSouliveはますます、絶好調です。オルガン・トリオという、ジミー・スミスがポピュラーにしたフォーマットにまだまだ大きな可能性があるということを、提示した彼らですが、そのサウンドの中核をなしているのは、ファンク、モータウン・サウンドから、ジャコまであらゆるベース・ラインを研究した、ニールの左手と、エルヴィン・ジョーンズがフェイヴァリット・ドラマーと言いながら、ヒップ・ホップの洗礼を受けた、アランのタイトで強
NYのインディ・レーベル、ヴェロアからでたファーストアルバムのアートワークも、60年代ブルーノートを意識していた彼らから見れば、Dream
comes trueといったところでしょうか。メジャー契約と、ツアーが一段落つく秋には、セカンド・アルバムのレコーディングが決まったSouliveはますます、絶好調です。オルガン・トリオという、ジミー・スミスがポピュラーにしたフォーマットにまだまだ大きな可能性があるということを、提示した彼らですが、そのサウンドの中核をなしているのは、ファンク、モータウン・サウンドから、ジャコまであらゆるベース・ラインを研究した、ニールの左手と、エルヴィン・ジョーンズがフェイヴァリット・ドラマーと言いながら、ヒップ・ホップの洗礼を受けた、アランのタイトで強 烈なドラミングのコンビネーションでしょう。その凄まじいドラミングは、時にスネア・ドラムのヘッドも貫き通すパワーを誇ります。このタイトなリズムの上で、ニールの右手や、エリックのギターが歌うシンプルながらキャッチーなメロディが彼らを東海岸No.1のダンス・バンドに押し上げたと言えます。エリックのカッティングや、多彩なペダル・ワークも、ややもすると単調になりがちなサウンドに、強い色彩を加えています。
烈なドラミングのコンビネーションでしょう。その凄まじいドラミングは、時にスネア・ドラムのヘッドも貫き通すパワーを誇ります。このタイトなリズムの上で、ニールの右手や、エリックのギターが歌うシンプルながらキャッチーなメロディが彼らを東海岸No.1のダンス・バンドに押し上げたと言えます。エリックのカッティングや、多彩なペダル・ワークも、ややもすると単調になりがちなサウンドに、強い色彩を加えています。
この頃、日本でもSouliveの輸入盤が、タワー・レコードでじわじわと売り上げを伸ばし始め、輸入販売元のレコード会社のオフィスでも「この夏は、いけソウライヴ」という合い言葉が使われていました。9月のNHKBSのオンエアを契機に大ブレイクへと突入したわけですが、おりしもJam
Bandというムーヴメントが、日本でも噂に上るように、なり始めました。
8月に私は、Jam Bandムーヴメントのなかで、もっとも大きなイベントである、バークシェア・マウンテン・ミュージック・フェスティヴァルに派遣されました。昨年で3回目を迎えた、キャンプ形式の3日間のイベントで、MM&W、ギャラクティック、ディープ・バナナ・ブラックアウト、DJロジック、ストリングス・チーズ・インシデント、そしてSouliveと注目のバンドが目白押しの、濃いフェスティバルです。この模様は、昨年のジャズライフ10月号のNYリポートで取りあげましたが、Souliveは、またも真夏のスキー・ロッジを大ダンス・フロアに、変えたのでした。また、日本からやって来たライターのS氏、NY在住のM君と、Soulive、MMWにじっくりインタビューをする機会をえました。
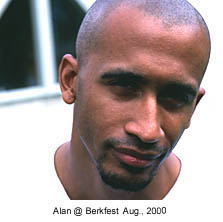 |
 |
 |
リーダーのアランは、高校卒業後、様々なバンドでツアー・サーキットをこなして鍛えられた、叩き上げ。その弟のニールは、兄を頼ってNYに出てきたあと、マンハッタン音楽院に通ったそうです。もともとピアニストで、同級生には、ジェイソン・モランや、ステフォン・ハリスら、ブルーノートのヤング・ライオン達がいて大いに啓発されたとのこと。クラッシックにも造詣が深く、ピアノを弾くとまったく別人のプレイをするそうです。この二人が満を持して始めたユニット”Soulive”に欠けていた、最後の1ピースが、エリックです。、学生時代から、ボストン近辺で評判のファンク・バンド、”レタス”で活躍していたエリックは、たった一度のセッションで意気投合し、大学卒業後Souliveに就職と、あいなりました。彼ら、20代半ばのジャズの世界の新世代と話していると、前世代の音楽に対するリスペクトとともに、 かつてマイルス・デイヴィスがそうであったように、あらゆる音楽が、”クール”かどうか?という基準で、何の偏見もなく頭の中で共存していることに気がつきます。これが、高度なインプロヴィゼーションを繰り広げながら、難解に陥ることなく、若い世代の支持を得ている、理由でしょう。
かつてマイルス・デイヴィスがそうであったように、あらゆる音楽が、”クール”かどうか?という基準で、何の偏見もなく頭の中で共存していることに気がつきます。これが、高度なインプロヴィゼーションを繰り広げながら、難解に陥ることなく、若い世代の支持を得ている、理由でしょう。
このフェスティバル中に2回ライヴをこなしたSoulive。両方とも超満員で、熱気ムンムンでした。スキー・リゾートのため、エアコンがなく、いつもは、黒のクラッシック・スーツで決めている彼らも、この時ばかりはスーツを諦め、ストリート調のカジュアルなスタイルで、盛り上げました。DJロジックもジョイントした、ナイト・クラブの演奏は、PAの不調で、ロジックの音がまったく聴こえないというアクシデントもありましたが、ニールが、完全にぶっち切れたプレイを聴かせてくれました。 東京ベースのライターとしては、初めて生でSouliveを見たS氏も、今、東京に連れていっても相当いけるんじゃないの、と語っていましたが、それは、今年(2001年)の2月まで、待つことになります。
東京ベースのライターとしては、初めて生でSouliveを見たS氏も、今、東京に連れていっても相当いけるんじゃないの、と語っていましたが、それは、今年(2001年)の2月まで、待つことになります。
9月に、初めて西海岸ツアーをこなし、セカンド・アルバムのための新曲の準備も、着々と進んでいる頃、日本では、ファースト・アルバム"Turn
it out"が売り上げが1万枚を突破し、タワーレコードの、邦楽も含めたチャートでも、Top30にランクインするという、大ブレイクが始まりました。NHKBSのオンエアも、強力に後押ししています。インスト物では、異例の大ヒットです。私自身、このバンドは、日本で受けるとは、思っていましたが、ここまでいくとは思いませんでした。インディ盤のため、インターネット通販と、ライヴでの手売りがメインだったアメリカでの売り上げを、まだ一度も来日していないにもかかわらず、日本での売り上げが、凌駕しました。アメリカでも、NYで唯一、店頭で売られていたタワーレコード・ビレッジ店では、ジャズ・チャートで最高位が3位、長い間、Top10をキープしており、NYのヒップなリスナーの支持を、勝ちえました。この”Turn
it out”は、エリックの実兄ジェフ・クラズノーが経営するインディ・レーベル、ヴェロア・レコーディングスの、最初のビッグ・プロジェクトでもありました。99年の3月のバンド結成から、録りためた数々のライヴ音源と、何度も自社スタジオで様々な曲を試し、6ヶ月の時間をかけて熟成されたアルバムです。1曲目”Steppin’”の、冒頭のオルガンのワンフレーズが、すべてを凝縮していて、リスナーの気持ちをがっちりとつかみます。このワンフレーズで、大ヒットを生み出したといっても過言では、ありますまい。私が、昨年もっともよく聴いたアルバムです。セカンド・アルバムへの期待は高まりました。
 10月に、数々の名作が録音された、アヴァター・スタジオ(旧パワー・ステーション)を、4日間ブッキングして行われた、セカンド・アルバム”Doin'
Something”のレコーディングは、JBホーンズの中核メンバーだった、フレッド・ウェズリーが、ホーン・アレンジを提供し、ホーンセクションをリードしました。ヴォーカル・チューンや、ピアノ、キーボードのオーヴァー・ダブで、作りこんだ曲が入りました。7月ぐらいのライヴでは、メニューに入っていた曲も多く、3人のコンビネーションは、ばっちりまとまっています。Souliveならではの、ライヴなグルーヴを捉えた曲もあり、かなりバラエティに富んだ、内容のアルバムです。ニールは、嬉々としてピアノを弾いています。日本盤の一番最後で、ちょっとだけソロピアノを聴けるのはご愛敬です。このレコーディングでも、アランのタイトなドラムが、サウンド・キーを占めています。撮影中に、リハーサルに突入し、ドラム・ブースの中で聴いたそのサウンドは、ヒップ・ホップのメリハリが利いた中にも、トニー・ウィリアムスを思わせるような繊細さが同居しています。90年代以降に登場した新しいタイプのドラム・スタイルです。エリックも、オーヴァー・ダブによって、多彩なカッティング技を聴かせてくれています。しかし、私の好みでは、”Turn
it out”の方が、このバンドのヴィヴィッドな瞬間を的確に記録していうように思えます。結局、これはテクノロジーとクリエイティヴィティの狭間で、そのバランスをとるのが如何に難しいかという問題をはらんでいます。
10月に、数々の名作が録音された、アヴァター・スタジオ(旧パワー・ステーション)を、4日間ブッキングして行われた、セカンド・アルバム”Doin'
Something”のレコーディングは、JBホーンズの中核メンバーだった、フレッド・ウェズリーが、ホーン・アレンジを提供し、ホーンセクションをリードしました。ヴォーカル・チューンや、ピアノ、キーボードのオーヴァー・ダブで、作りこんだ曲が入りました。7月ぐらいのライヴでは、メニューに入っていた曲も多く、3人のコンビネーションは、ばっちりまとまっています。Souliveならではの、ライヴなグルーヴを捉えた曲もあり、かなりバラエティに富んだ、内容のアルバムです。ニールは、嬉々としてピアノを弾いています。日本盤の一番最後で、ちょっとだけソロピアノを聴けるのはご愛敬です。このレコーディングでも、アランのタイトなドラムが、サウンド・キーを占めています。撮影中に、リハーサルに突入し、ドラム・ブースの中で聴いたそのサウンドは、ヒップ・ホップのメリハリが利いた中にも、トニー・ウィリアムスを思わせるような繊細さが同居しています。90年代以降に登場した新しいタイプのドラム・スタイルです。エリックも、オーヴァー・ダブによって、多彩なカッティング技を聴かせてくれています。しかし、私の好みでは、”Turn
it out”の方が、このバンドのヴィヴィッドな瞬間を的確に記録していうように思えます。結局、これはテクノロジーとクリエイティヴィティの狭間で、そのバランスをとるのが如何に難しいかという問題をはらんでいます。 もちろん”Doin' something”は、新人アーティストの、メジャー・デビュー作品として、十分に高いクオリティを持っていますが、彼らのポテンシャルを考えると、もっと荒削りでもよかったのではとも思えます。”Steppin'’の冒頭のフレーズのような、キャッチーなメロディは、99年の状況の中で生み出されたものであり、彼らは、次のレベルでの挑戦を始めたのでしょう。”Doin'
Something”のエンディング(アメリカ盤)にこのフレーズが、このフレーズがリプライズするのは、そんな彼らの訣別の意思表示のような気がします。
もちろん”Doin' something”は、新人アーティストの、メジャー・デビュー作品として、十分に高いクオリティを持っていますが、彼らのポテンシャルを考えると、もっと荒削りでもよかったのではとも思えます。”Steppin'’の冒頭のフレーズのような、キャッチーなメロディは、99年の状況の中で生み出されたものであり、彼らは、次のレベルでの挑戦を始めたのでしょう。”Doin'
Something”のエンディング(アメリカ盤)にこのフレーズが、このフレーズがリプライズするのは、そんな彼らの訣別の意思表示のような気がします。
昨年の年末は、恒例のメイシオ・パーカーによる、アーヴィング・プラザのカウント・ダウン・ライヴの前座を務め、激動の一年の幕を閉じました。おそらく、Souliveが、アーヴィング・プラザで、ほかのアーティストのオープニングを務めるところは、これで見納めといったところでしょう。
1月は、アランに長男が誕生し、Souliveは活動一時停止。その間、エリックは、ウェットランズ・プリザーヴで、毎水曜のレジデント・セッションを行いました。Soulive参加前に、在籍した”レタス”を率いて、スペシャルゲストに、ジョン・スコフィールド、フレッド・ウェスリー、DJロジック、ジェイムス・ハートを迎えての大盛り上がり大会でした。この模様は、ジャズライフ3月号にリポートしましたが、またこのコーナーでも取りあげるつもりです。エリックは、若くして完成されたギタリストですが、この様なセッションを重ねることによって、まだまだ延びる可能性を秘めています。その将来に大きな期待がもてます。
そして、彼ら自身も待ち望んでいた、日本ツアー。ブルーノートのチケットは、ことごとくソールド・アウトとなり、ファースト・アルバムも2万枚に届こうかという状況でしたが、彼ら自身もまだ、実感が湧かないようでした。ブルーノートは、フランス料理がサーヴされる高級店だよ、と脅かしておいたら、エリックは、もしも誰も立ち上がって踊らなかったらどうしようと、ビビっていました。しかし実際は、すべてのブルーノートをダンスフロアに変えてしまう大フィーバーだったことは、ご存じの通りです。パフォーマンスのあとは、毎回のサイン攻め。日本先行発売された、セカンド・アルバム”Doin'
Something"は、一週間で1万5千枚を越す、大ヒット街道を驀進中と、アメリカでは、体験したこと がない大きな支持を、日本のリスナーから受けました。Souliveの音楽にリスペクトを払い、心から楽しんでくれた日本のリスナーにいたく感激したとのことです。
がない大きな支持を、日本のリスナーから受けました。Souliveの音楽にリスペクトを払い、心から楽しんでくれた日本のリスナーにいたく感激したとのことです。
大成功のうちに終わった、最初の日本ツアーからアメリカに戻ると、いよいよ”Doin' Something”の全米リリースです。発売と同時に、全米ジャズ・チャート、ラジオ・チャートの、Top5にランクイン。CDショップも軒並み、平積みでディスプレイをし、メジャー・レーベルの底力を見せつけます。アーヴィング・プラザでは、新譜発売記念ライヴを、ホーンセクション、ヴォーカルのステファニー・マッケイを迎えて2日間おこないました。思えば、ちょうど一年前、ジョン・スコフィールドの、オープニング・アクトをつとめていたSouliveは、今度は、スクリーミン・ヘッドレス・トーソス、スクワァッドを従えた、メイン・イベンターヘと駈け上りました。
5月は、ロック・スターのデイヴ・マシューズのスタジアム・ツアーの前座を務めました。マシューズが、異例ながらオープニングに現れ、今一番ファンキーで、俺が気に入っているバンドと、紹介する一幕もあり、数万人に及ぶ観衆を興奮の坩堝にたたき込みました。アメリカでも、着実にスターダムの階段を、上っています。今年も、Souliveの熱い夏が、始まります。
私自身は、昨秋のレコーディングあたりから、Souliveへの思い入れは、注目して欲しい若手グループとして応援するというスタンスから一歩引いて、完成されたグループへのリスペクトへと、変わっていきました。最近、Souliveの演奏を聴いても、昨年ほどグッとこないのは、彼らのスタイルが洗練されてきたのと同時に、私の心情変化もあるのでしょう。しかし、Souliveはこれからも、成長を繰り返し、またあの衝撃を与えてくれると確信しています。また彼らに続く、ニュー・カマーを求めて、NYアンダーグラウンド・シーンに、ハングアウトし続けようと、思っています。Souliveとの一年は、私が無我夢中で音楽に触れて写真を撮っていた、15年前の初心を思い出させてくれました。
関連リンク